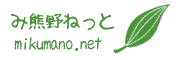平家打倒の謀議が露見、その首謀者・藤原成親は流罪に
1 平清盛の熊野詣 2 藤原成親の配流 3 成経・康頼・俊寛の配流 4 平重盛の熊野詣
5 以仁王の挙兵 6 文覚上人の荒行 7 平清盛出生の秘密 8 平忠度の最期
9 平維盛の熊野詣 10 平維盛の入水 11 湛増、壇ノ浦へ 12 土佐房、斬られる
13 平六代の熊野詣 14 平忠房、斬られる
熊野権現の加護を受けた平清盛は、保元の乱・平治の乱で功を上げ、後白河上皇に引き立てられ、後白河上皇のもと、異例の昇進をし、権力をほしいままにしました。そのため、貴族たちの反感を買いますが、藤原摂関家の力を弱め、院の権力を強化することが後白河上皇の清盛重用の狙いでした。
その狙い通りに院の権力強化に多大な貢献を果たした清盛および平家一門でしたが、朝廷の中枢を独占した平家一門の思い上がり、傲慢な振る舞いには、平家を引き立ててきた当の後白河上皇やその近臣にも反感を抱かれてしまう始末。平家一門はあまりに強大になりすぎました。
大納言藤原成親(なりちか。1138~79)を中心とする後白河上皇の近臣たち(俊寛僧都、西光法師、平康頼ら)は、京東山の麓の鹿の谷(ししのたに)にある俊寛僧都の山荘に集い、平家打倒を謀議するようになります。その謀議には、ときに後白河上皇の参加もありました。
しかし、その企てが密告により事前に露見してしまいます。激怒した清盛はすぐさま計画の首謀者たちを、後白河上皇を除き、捕らえ、処罰します(いわゆる鹿の谷事件。1177年のこと)。
西光法師は拷問の上、斬殺されました。その子らも殺されてしまいます。
首謀者の藤原成親は、当然死罪になるべきところを成親の妹を妻にしている平重盛(清盛の嫡男)の必死の説得によって流罪となります。
成親の嫡男・成経(なりつね)も捕えられ、やはり流罪に。
成親は備前(岡山)の児島に流され、成経は、平康頼・俊寛僧都の2人とともに、薩摩(鹿児島)の南方海上にうかぶ鬼界ケ島(きかいがしま)に流罪になりました。
『平家物語』巻二「新大納言の流されの事」より一部現代語訳
西八条の清盛邸から西へ出て、朱雀大路を南へ行くと、成親はいつも参内していた皇居をも今は遠い場所に見て通り過ぎなさった。長年、見なれもうしあげた雑色・牛飼にいたるまでみな、涙を流し、袖を濡らさぬ者はなかった。まして都に残り留まりなさる北の方や幼い子供たちの心のうちが推し量られて哀れである。
鳥羽殿(京都の南方鳥羽にあった城南離宮)をお過ぎなさるときにも、「この御所へ法皇がおいでになるときには一度もお供から外れなかったものを」と思い、「洲浜殿」という自分の山荘があったのだが、それをも遠くに見てお通りなさった。
やがて鳥羽殿の南門に出て、船が遅いと急がせた。
大納言が「同じ殺されるのならば、都近くのこのあたりで殺してくれよ」とおっしゃったのも、よほどの事である。
近くに添いもうしあげた武士を、「誰か?」と問いなさると、「預かりの武士、難波次郎経遠」と名乗りもうしあげた。
「もしかしたらこの辺りに私の知り合いの者はいるだろうか。一人、尋ねて参上させよ。舟に乗らぬ先にいっておきたいことがある」とおっしゃるので、経遠はその辺りを走り回って尋ねたけれども、「我こそは大納言のお知り合いである」と申す者はひとりもいなかった。
そのとき、大納言は涙をはらはらと流して、「それにしても、私が世にあったときには、従いついていた者どもは1000人2000人はいただろうに、今は、それとなくでもこの有り様を見送る者がいない悲しさよ」といって泣かれたので、猛き武士どももみな、鎧の袖を濡らした。ただ成親の身についてくる物といえば尽きせぬ涙ばかりである。
成親ほどの身分であれば、熊野詣・天王寺詣などには、二つの龍骨のある屋形を三段に造った大きな船に乗り、後続の船を20~30隻も続けていたものだが、今はみずぼらしい、屋形を仮に据え付けた舟に、大幕を引き、見なれぬ兵どもに連れられて今日を最後に都を出て、波路遥かに赴かれた心のうちが推し量られて哀れである。
(現代語訳終了)
成親は配流先で
藤原成親は後白河上皇のお気に入りで、熊野御幸にも幾度か従っているようで、『梁塵秘抄口伝集』にも成親の名は見えます。熊野御幸のときには城南離宮で身を清めてから船に乗り、淀川を下りましたが、 配所へも城南離宮から船に乗せられて移送されました。
成親は一旦は備前の児島に置かれますが、じきに内陸の備前備中の国境にある有木の別所という山寺に身柄を移されます。そして、その配所で成親は出家しましたが、その後、密かに殺されてしまいました。
(てつ)
2019.9.3 更新
参考文献
- 佐藤謙三校注『平家物語 (上巻)』角川文庫ソフィア
- 梶原正昭・山下宏明 校注 新日本古典文学大系『平家物語(上)』岩波書店