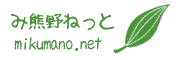世界的博物学者、南方熊楠の旧邸

南方熊楠(みなかたくまぐす)。慶応3年(明治になる前年、1867年)4月15日、紀州生まれ。
日本が近代化に躍起になっていた明治から昭和の初期という時代にあって、18ヶ国語を解し、博物学、生物学、民俗学、宗教学、性愛学、エコロジーなどの様々な分野の学問を行き来し、異能を発揮した世界的博物学者です。
日本の変形菌(粘菌)分類学の基礎を固めた生物学者であり、また柳田国男とともに日本の民俗学を創始した民俗学者でもありました。

生まれは紀州和歌山城下。幼少時から『和漢三才図絵』全巻を筆写するなど、熊楠は和漢書により学問的基礎を形成していきました。和歌山中学卒業後、東京大学予備門に入学しますが(同期に夏目漱石、正岡子規など)、20歳で中退。アメリカに渡り遊学、隠花植物(菌類、地衣類、藻類、蘚苔類など)や粘菌を求めて各地を点々します。

26歳でイギリス、ロンドンへ。ロンドンでは大英博物館で東洋関係資料の整理を手伝いをする仕事を得、また大英博物館の資料閲覧を許され、博物学・民俗学などの書物を筆写し、古今東西の知識を吸収。科学雑誌『ネイチャー』や随想問答雑誌『ノーツ・エンド・キリース』にしばしば論文を寄稿し、掲載され、欧米の学者に注目され、名声を高めます。またロンドンでは孫文と親交を結びます。

14年に及ぶ海外遊学の後、1900年(明治33年)、34歳で帰国。熊野の那智山を中心に植物の調査を始めます。3年の植物調査の後、1904年(明治37年)、口熊野、田辺を訪れ、田辺の中屋敷町に家を借り、定住しました。その2年後の1906年(明治39年)、40歳で闘鶏神社の神官の娘の田村松枝と結婚。1男1女をもうけます。

田辺では、隠花植物や粘菌の研究の傍ら、国内外に民俗学関係などの論文を発表(熊楠は那智や田辺という日本の辺地にあっても、『ネイチャー』や『ノーツ・エンド・キリース』に寄稿を続け、『ネイチャー』には1914年まで、『ノーツ・エンド・キリース』には1933年まで論文を発表しています)。
しかし、ちょうど熊楠が結婚した年に施行された1町村1社を原則とする神社合祀令が熊楠の植物研究に影を落とします。
明治政府は記紀神話や延喜式神名帳に名のあるもの以外の神々を排滅することによって神道の純化を狙いました。

熊野信仰は古来の自然崇拝に仏教や修験道などが混交して成り立った、ある意味「何でもあり」の宗教ですから、合祀の対象となりやすかったのでしょう。村の小さな神社が廃止されただけでなく、歴代の上皇が熊野御幸の途上に参詣したという歴史のある熊野古道・中辺路の王子社までもが合祀され、廃社となり、神社林が破壊されました。
熊楠にとって神社林は貴重な生物が住む貴重な研究の場所であり、神社合祀の嵐が熊野に吹き荒れるなか、熊楠は神社林が破壊されることに怒りを爆発させ、神社合祀反対運動に立ち上がりました。地方新聞に神社合祀反対意見を投書し、住民を説得に出かけ、中央の学者に書簡で訴えるなど、神社合祀に対して死にもの狂いで闘いました。留置場に拘留され、罰金を課せられるなどの目に会いながら熊楠は命をかけて闘いました。

熊楠の神社合祀反対運動が報われたのが、熊楠63歳、1929年(昭和4年)の昭和天皇への粘菌学の進講。熊楠が保護に努めた田辺湾に浮かぶ神島(かしま)に天皇を迎え、御召艦長門上で進講。粘菌標本110点を熊楠が進献しました。
翌1929年(昭和4年)に神島は県の天然記念物に指定され、1936年(昭和11年)には国の天然記念物に指定されました。
1941年(昭和16年)12月29日、熊楠死去。75歳。田辺郊外の真言宗高山寺に埋葬されました。
神社合祀令により熊野(和歌山県・三重県)の神社の8割から9割が滅却され、神社林が伐採されたといいますが、熊楠の働きかけにより神島、那智原始林、野中の一方杉、引作の大クス、闘鶏神社、八上神社、田中神社などの森や木が守られました。熊楠がもし熊野にいなかったら、それらの森もなくなっていたのかもしれないと思うとゾッとします。熊野に熊楠がいてほんとうによかったと思います。

熊楠が1916年(大正5年)以降1941年(昭和16年)に永眠するまで終の住まいとした邸が現在も田辺市中屋敷町に保存されています。
それまで借家住まいだった熊楠は1916年、50歳のときに田辺の中屋敷町に家を弟名義で購入。
約400坪の敷地には2階建ての母屋があり、土蔵があり、貸家2軒などがありましたが、熊楠は前に住んでいた借家に自分の設計で建てた「博物標本室」をここに移築し、書斎としました。(左の写真は書斎。現在の南方熊楠邸には母屋、土蔵、書斎が現存します。貸家2軒はなく、熊楠没後に新たに建てられた2階建ての別棟があります)。
熊楠邸内の様子をもっと画像でご紹介したいので、続きは次頁に。
南方熊楠について詳しくは南方熊楠のキャラメル箱へ
(てつ)
2003.5.5 UP
2025.6.30 更新
参考文献
- 中沢新一責任編集・解題『南方熊楠コレクション〈第4巻〉動と不動のコスモロジー』 河出文庫
- 中沢新一 責任編集・解題『南方熊楠コレクション〈第5巻〉森の思想』 河出文庫
- 中沢新一『森のバロック』 せりか書房
- 鶴見和子『南方熊楠』 講談社学術文庫
- 松居竜五・月川和雄・中瀬喜陽・桐本東太=編『南方熊楠を知る事典』 講談社現代新書
- 神坂次郎『縛られた巨人 南方熊楠の生涯』 新潮文庫
- 『南方熊楠 新文芸読本』 河出書房新社
- 『太陽』1990年11月号 No.352 平凡社
- 『超人 南方熊楠』朝日新聞社
- 水木しげる『猫楠 南方熊楠の生涯』 角川文庫ソフィア
南方熊楠邸へ
アクセス:JR紀伊田辺駅から徒歩15分
駐車場:駐車場あり
詳しくは南方熊楠顕彰館・南方熊楠邸HPへ
観光プラン