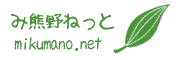三百年以上の古樟、実に健康状態にありしものを根から掘り、砕片となし樟脳を作りおり

田辺市指定天然記念物「鬪雞神社のクスノキ(2本)」のうちの1本
闘鶏社へちょっと遊びに行き候ところ、三百年以上の古樟、実に健康状態にありしものを根から掘り、砕片となし樟脳を作りおり、よってその筋に抗議候も跡の祭り、右は老朽木として見分相済み、前々月中に伐採を許可せしという。はなはだしき不都合と存じ、いろいろ取り調べ候ところ、今二本、二百年ばかりの樟、少しも朽ちたる点なきをもすでに伐採許可、同じく老朽木とし有之(これあり)、よって抗議し、かの詐偽輩大いにおそれ入り候。
ー 柳田國男宛書簡、明治44年6月18日付『南方熊楠全集』8巻
南方熊楠は神社合祀関連の文章のなかでは樟脳についてほとんど触れていません。『南方熊楠全集』に収められた神社合祀関連の文章のなかで樟脳について触れている箇所がおそらくここだけです。
闘鶏神社(正式な表記は鬪雞神社)は南方熊楠邸から徒歩10分ほどの所にあり、その森は熊楠が「熊野植物精査西牟婁郡の分の基点」とした場所でした。闘鶏神社は熊野信仰において熊野三山に次いで重要な位置にある神社ですので合祀されることはありませんでしたが、それでも神社の森の木が伐採されました。
役所には老朽木だと詐偽の申し立てをして役所から許可を得ての伐採です。合祀されなかった由緒ある神社でもこのような無法な伐採が行われました。いかに熊野で行われた神社の森の破壊がひどいものであったかが想像できます。
伊勢と熊野がある三重県・和歌山県の2県で正当な理由もない神社合祀がもっともひどく行なわれたのは珍事だと南方熊楠は憤りました。
(「三重と和歌山の二県で、由緒古き名社の濫併、もっとも酷く行なわれたるぞ珍事なる」
)
三重県・和歌山県の2県で神社合祀を厳しく行った理由はいくつかあると思われますが、ひとつの理由に樟脳があったのではと想像します。 樟脳は楠から製造されます。
当時、明治政府は神道を宗教ではなく国家の祭祀だとして、以前のものとは異なる新たな神道を国民に普及させようとしていました。新たな神道は国家のためのものなので神社に対しては国や地方自治体から金銭的な援助を行うということになりました。
しかしながら日露戦争により莫大な借金を抱えた明治政府は財政支出削減のために神社への援助を減らすことを考えました。そのために日露戦争終結の翌年から実施されることとなったのが神社合祀です。財政的に負担できるまでに神社の数を減らすということが神社合祀の目的でした。
政府は支出を切りつめるだけではなく、収入を増やすこともしなければなりませんでした。そこで目をつけられたのが三重県と和歌山県の神社だったのではないか、と私は考えます。
三重県と和歌山県の神社には国の収入を増やすものがありました。楠です。国が三重県・和歌山県の神社に生える楠の伐採を求めたために両県でとくに激しい神社合祀が行われたのではないでしょうか。
当時、日本は世界最大の樟脳の輸出国でした。日本は、国内のみならず、当時植民地であった台湾で楠のプランテーションの経営を行い、樟脳の生産に力を入れていました。
樟脳は楠の木片を蒸して作られます。樟脳のことをカンフルと言いますが、樟脳は強心剤として使用され、またセルロイドの原料のひとつでもあり、眼鏡のフレームやおもちゃ、映画や写真のフィルムに使用されました。
明治政府が樟脳を専売化して国が生産・流通・販売を全面的に管理して利益を独占する体制にしたのが明治36年(1903年)です。その3年後の明治39年(1906年)に神社合祀政策の法的な基盤が整えられました。その間に日露戦争があり、その結果、日本は巨額の借金を抱えました。
日露戦争のさなか、戦費調達のために政府はタバコの専売を強化し、塩の専売も開始しました。専売にすると、国が販売価格を決定できるので高い価格をつけて販売することができ、国の財政収入を増やすことができます。タバコや塩は国内での販売ですが、樟脳は海外に向けて輸出されるので、日本にとって樟脳は国の財政収入を増やすために重要な外貨獲得商品でした。
樟脳の製法は六世紀のアラビアで発明されたといわれ、日本に伝えられたのは十六世紀だと考えられています。樟脳の原料となる楠は、台湾、中国、ベトナムなど温暖な土地に生育する木です。日本では主に九州、四国、本州西部の太平洋側に分布します。どこにでも生える木ではありません。
日本で最初に樟脳製造を事業化したのは薩摩藩です。薩摩藩は樟脳を藩の専売としました。明治政府の樟脳の専売は薩摩藩に倣ったものです。薩摩藩の樟脳は江戸時代初期からヨーロッパや中国に輸出され、藩に利益をもたらしました。江戸時代の日本の主な輸出品は金銀銅と樟脳でしたが、樟脳に関しては、当時ヨーロッパで流通していた樟脳のほとんどが日本産で、そのほとんどが薩摩藩の物でした。樟脳は薩摩藩に莫大な利益をもたらしました。
その後、幕末になって土佐藩でも樟脳製造が盛んになりました。明治維新を推進した薩長土肥の四藩のうち、薩摩藩と土佐藩は樟脳を製造輸出していました。樟脳で得た利益は西洋式軍備の導入や明治維新へとつながっていったのでしょう。
紀州藩(和歌山県と三重県南部)は楠の生息地でありながら樟脳産業が発達しませんでした。熊野(和歌山県南部と三重県南部)では江戸時代初頭に山林の濫伐が行われましたが、それ以降、紀州藩は藩に必要な用材の確保のために領内の山林の保護育成に務めました。とくに建築や造船の用材として大材を必要とした楠、榧、欅の三種類の木については、藩が必要なときに必要なだけ伐採できるように、木の大小にかかわわらず、あるいは枯木であったとしても領民による伐採を禁じました。
それが明治になって自由に伐れるようになると、多数の土佐の樟脳業者たちが熊野に入り込んで、楠の濫伐を始めました。樟脳は樹齢が大きい楠ほど含有量が多くなり、通常樹齢五十年以上の楠から樟脳が製造されます。樟脳製造業者にとって原料である楠の確保が何よりも重要なことですが、土佐では明治初期にすでに原料にできる樹齢の楠を伐り尽くしてしまっていたので、楠が残された熊野の山林は宝の山であったことでしょう。
土佐の樟脳業者たちは濫伐を進め、そして、明治末期までに熊野の楠のほとんどを伐り尽くしました。明治末期には楠の大木はほとんど神社にしか残されていないような状況になっていたことでしょう。土佐の樟脳業者たちにとって神社は熊野に残る最後のフロンティアでした。だから楠が眠る熊野の、三重県と和歌山県の神社が狙われたのでしょう。
当時、樟脳精製の拠点は神戸にあり、内地産・台湾産ともに神戸で精製して、神戸港からイギリス、フランス、ドイツ、アメリカなどに輸出し、大正時代には世界シェアのおよそ七割を占めていました。日本にとって樟脳は重要な外貨獲得商品でした。後に樟脳産業は化学合成品の開発により衰退していきますが、日本が世界の樟脳市場を独占していた最中に神社合祀は推し進められました。
神社合祀は、地方自治体の神社への資金援助を実現させるために財政的に負担できるまでに神社の数を減らすという目的で実施された政策ですが、それと表裏一体に、神社の森の楠を伐って樟脳という商品に変えるという目的もあったようにうかがえます。

台湾総督府による専売樟脳の販売所の看板(樟脳 - Wikipedia)
寺人孟子 - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, リンクによる
熊野で神社合祀の嵐が吹き荒れたちょうどその頃、植民地の台湾でも楠の確保が難しくなり、先住民が生活する山地に楠を求めていかなければならなくなりました。台湾総督府は高電圧鉄条網や砲台、地雷などを使用して台湾先住民を封じこめて、楠を確保しました。総督府はさらに包囲網を狭めて追い込み、武装抵抗を誘っては制圧し、さらに先住民の生活圏を狭めていきました。台湾総督府は明治42年(1906年)から5年かけて総攻撃を行い、先住民を高山に追いつめ、餓死か降伏を迫り、そして台湾の山地の残された楠を手に入れました。
もちろん熊野での神社合祀はこれほど残虐非道なものではありませんでしたが、国の狙いは古い神道の破壊とともに、楠の確保にあったのではないでしょうか。台湾先住民の生活する山地も熊野地方の住民が心の拠り所とする神社の森も、国にとっては樟脳の原料である楠が眠る宝の山でしかなかったのでしょう。
熊楠は三重県と和歌山県でとくに激しい神社合祀が行われた理由を述べていません。樟脳がその理由のひとつであるように思われますが、熊楠は神社合祀反対の訴えのなかで樟脳には触れていません。
熊楠がやらなければならなかったのは、神社合祀を止めることでした。熊楠は現実に神社合祀を止めるにはどうしたらよいかということを考えて行動し、文章を発表しました。国の専売である樟脳事業の非道を訴えても、国相手では勝ち目はありません。そのようなことよりも熊野地方の神社にどれだけ貴重な生物が生息するか、どれほど文化的にも価値のあるものなのかを伝え広めることのほうが神社合祀を止める力となり得ると熊楠は考えたのでしょう。
熊楠は国相手には直接は戦っていません。県や郡村の役人が国の方針に従わずに無茶苦茶な神社合祀を強引に推し進めているのだというスタンスで熊楠は戦いました。その県や郡村の役人による無茶苦茶な神社合祀も私利私欲のための暴走などではなく、実際には政府の意向を受けてのことなのだと思われますが、神社合祀を止めるには国に動いてもらわなければならないので、国を直接に敵に回さないような戦い方を熊楠は行っていたのだろうと思います。
(てつ)
2025.6.30 UP
参考文献
- 『南方熊楠全集』8巻、平凡社