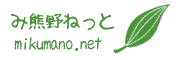熊野から持ち帰った小石が成長
京都を出発し、船に乗って淀川を下り、現在の大阪市天満橋の辺りで上陸。海岸筋の熊野街道を熊野の玄関口、口熊野といわれた田辺まで南下。
田辺からは中辺路(なかへち)の山中の道を本宮へ向かう。本宮からは熊野川を船で下り、熊野川河口にある新宮に詣る。新宮からは再び徒歩で海岸線沿いを辿り、それから那智川に沿って那智に登っていく。那智からは再び新宮を経、熊野川を遡行するか、あるいは那智の背後にそびえる妙法山に登り、大雲取越え・小雲取越えの険路を越えるかして本宮に戻り、再び中辺路を通って都に帰っていく。
これが京からの熊野詣の順路でした。往復約600km、およそ1ヶ月かけて歩き、熊野を詣で、京へ帰っていきました。
那智から本宮へ向かう「大雲取越え、小雲取越え」は西国三十三所観音巡礼のメインルートです。
西国三十三所観音巡礼が盛んになる以前の中世の文献には唯一、 後鳥羽上皇の4回目の熊野御幸に従った藤原定家が記した『後鳥羽院熊野御幸記』に見られるのみで、中世においては、那智からは新宮へ戻り熊野川を遡行して本宮に戻るというのが通常のルートでした。
「大雲取越え、小雲取越え」は、今は2日かけて歩くのが一般的ですが、昔の人は1日で歩いたそうで、後鳥羽上皇の熊野御幸にお供した藤原定家も「大雲取越え、小雲取越え」を1日で越え、日記『後鳥羽院熊野御幸記』に、
終日嶮岨を超す。心中は夢の如し。いまだかくの如きの事に遇わず。雲トリ紫金峰は手を立つるが如し。
などと記しています。よっぽどしんどかったのでしょう。
「大雲取越え、小雲取越え」は、また「死出の山路」とも呼ばれ、そこを歩いていると、亡くなったはずの肉親や知人に出会うといわれています。疲労困ぱいのなか、幻覚を見るのでしょうか。昔は行き倒れになった人も多かったらしいです。ダルという妖怪に取り憑かれたという話も伝えられています。
紀州が生んだ世界的博物学者南方熊楠(みなかたくまぐす)も雲取を歩いていてダルに取り憑かれたことがあるといいます。
予、明治三十四年冬より2年半ばかり那智山麓におり、雲取をも歩いたが、いわゆるガキ(※ダルのことです)に付かれたことあり。寒き日など行き労れて急に脳貧血を起こすので、精神茫然として足進まず、一度は仰向けに仆れたが、幸いにも背に負うた大きな植物採集胴乱が枕となったので、岩で頭を砕くを免れた。それより後は里人の教えに随い、必ず握り飯と香の物を携え、その萌しある時は少し食うてその防ぎとした。
(南方熊楠「ひだる神」)
南方熊楠は、同じ文章中に、菊岡沾涼の『本朝俗諺志』という書物からダルに関する話を引用していますので、それを口語訳して紹介します。
紀伊国熊野に大雲取、小雲取という二つの大山がある。この辺に深い穴が数カ所あり、手頃な石をこの穴に投げ込むと鳴り響いて落ちていく。2、3町(1町は約109m)、行く間、石の転がる音が鳴りつづけているという限りのない穴である。
その穴に餓鬼穴というのがある。ある旅の僧がこの場所で急に飢餓感に襲われ、一歩も足を動かせないほどになった。ちょうどそのとき、里人がやってくるのに出会い、「この辺で食べ物を求められるところはありますか、ことのほか腹が減って疲れています」というと、里人は「途中の茶屋で何か食べなかったのですか」という。
「だんごを飽きるまで食べました」と僧はいう。「ならば道の傍らの穴を覗いただろう」と里人。「いかにも覗きました」と僧がいうと、「だからその穴を覗くと必ず飢えを起こすのです。ここから7町ばかり行くと小さな寺があります。油断したら餓死してしまいます。木の葉を口に含んで行きなさい」と里人。
教えのようにして、かろうじてその寺へ辿り着き、命が助かった、という。(南方熊楠「ひだる神」、口語訳てつ)
かくのごとく険しい道なので(とくに大雲取越えがきつい)、「大雲取越え、小雲取越え」を歩く場合は、2人以上で歩かれることをお勧めします。
ところで、今の「大雲取越え、小雲取越え」は正式なルートではなかったようです。
『続風土記』によると、大雲取山を越え、小雲取を越える(小雲取山という山は具体的にはありませんが)その途中、如法山から東に方向を変え、「番西(ばんぜ)道」という番西峠(現在は万才峠と書く)を越える道を通り、志古(しこ)に出、熊野川沿いに大津荷(おおつが)、請川(うけがわ)を辿るというルートが本道だったそうです。
定家がお供をした後鳥羽上皇の熊野御幸のルートもこれでした。今の小雲取越えは後世に開かれた道だということです。西行も番西道を使って本宮に戻っています。
(てつ)
2020.8.7 更新
参考文献
- 丸山静『熊野考』 せりか書房
- 中沢新一責任編集・解題『南方熊楠コレクション〈第2巻〉南方民俗学』 河出文庫 引用箇所は312ページ