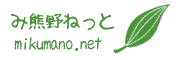室町幕府第6代将軍・足利義教が開基した龍穏寺の鎮守社

東武越生線越生駅より黒山行きバス乗車、上大満下車徒歩20分。
龍ヶ谷川に沿って進んでゆくと、参道を経て古刹龍穏寺の立派な山門に導かれる。
その脇、一の鳥居、二の鳥居の奥に鎮座。

一の鳥居

二の鳥居

御祭神
伊弉冉尊、速玉男尊、事解男尊
御由緒
社殿によれば明応元年に龍穏寺第三世住僧泰叟如康が紀州熊野本宮の産たるにより勧請し寺鎮守にしたという。
本殿は龍穏寺の境内社として五十六世・道海和尚の時代、天保十五年(1844)に再建されたもの。
拝殿と本殿がつながった権現造りである
(御祭神ともに埼玉県神社庁編「埼玉の神社」参照)
龍穏寺

龍穏寺
永享の頃(1429-1441)に将軍足利義教が上杉持朝に命じて尊氏以来の先祖の冥福と戦乱に果てた人々の霊を弔うために創立したものといわれている。
その後兵火にかかり、文明四年(1472)に太田道真、道灌父子によって再建された。境内には父子の墓がある。
天正十八年(1590)には、豊臣秀吉から御朱印百石を受け、次いで慶長17年(1612)には徳川幕府から、曹洞宗の関東三か寺を命じられ、国内二十三か国の曹洞宗寺院の世話をした。 また、江戸に寺地を賜り住職はそこに常在した公務を務めたという。
宝暦二年(1752)に火災によって堂塔を焼失し、天保十二年(1842)に再建されたが、大正2年の火災に よって、山門、経蔵、熊野社を残して全焼し、現存する本堂は戦後再建されたもの。
(TATSUさん)
No.513
2006.3.3 UP
2025.3.18 更新
参考文献
- 埼玉県神社庁編『埼玉の神社』