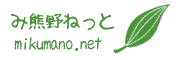熊野三社宮

JR武蔵野線三郷駅下車、徒歩約十分。
駅より南下、大場川を渡り看板に導かれ、小道を入った奥に鎮座。
一の鳥居、二の鳥居の奥、境内には社務所があり社殿が雪に埋もれていました。
境内はきれいに手入れされ、村の鎮守として歴史のありそうな神社でした。


御祭神
櫛御気野命(「埼玉の神社」参照)
社前の石碑には「熊野久須比命、伊邪那岐命、伊邪那美命」とありました。
御由緒
武蔵国の東部地域は、元荒川、古利根川、中川沿いの自然堤防上の古い村を除くと、ほとんどが近世初期に行なわれた新田開発により成立した村々で、当地もそれらのうちの一村で、文禄年間(1592-96)のころに信濃国佐久郡茂田井村の榎本藤右衛門という者が来て開墾したと伝えられている。
当社の創建は新田の開発もかなり進展した万治年間(1658-61)に行なわれたといわれている。
(「埼玉の神社」参照)


本殿
境内社
天満宮、金毘羅宮
その他
鳥居には安永六年(1778)の銘があり、手水舎にも弘化年間(1844-48)の銘がありました。
(TATSUさん)
No.511
2006.2.23 UP
2025.3.17 更新
参考文献
- 『埼玉の神社』